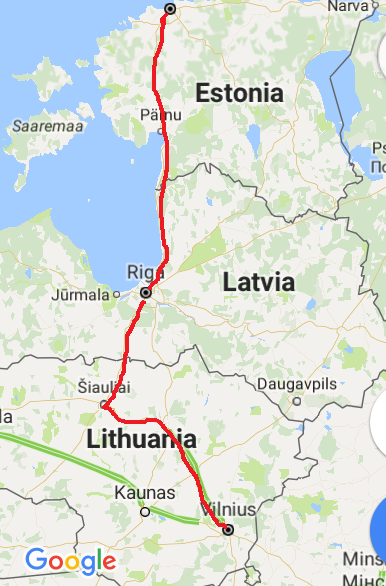地方出張からハノイに帰る飛行機が、暗く寝静まる中、一冊の本をむさぼるように読んだ。ベトナムに来る前に数日立ち寄った東京で、二日酔いの頭をかかえながらかっさらってきたツンドクの本のうちの一冊だ。いつ買ったかも覚えていないベトナム戦争の本。そこには、
「アジアの小国がまたドンパチやってやがる」くらいのイメージしかないのさ、アメリカの中の人々にとっちゃ。
みたいなことを書いた一説があった。ここまでもう20年も、中国だ日本だ韓国だベトナムだインドシナだと、たいして違いの分からないアジアの国々に、大戦だ独立だ反共だと、もろもろの戦争が起こっていたようだが、それはしょせんニュースが伝える遠い地の出来事に過ぎない、というようなことだ。
ああ2016年、今も同じだなと思う。日本の中の人々にとっちゃ、中東のドンパチがそれだ。「もうここ20年もクウェートだイラクだアフガンだレバノンだシリアだと、違いの良く分からない中東で、フセインだビンラディンだアサドだテロだISだと、もろもろの戦争が起こっているようだ」が、「たいていはニュースが伝える遠い地の出来事に過ぎない」まま、日々消費されていくのみだ。情報が発達しても人間の想像力は発達せず、いやむしろ退化するのかもしれない。

飛行機の中では読み終わらなかったので、ハノイに戻ってからも暇を見つけては読んでいた。さらさらと雨の降る午後にジュース屋の軒先で読み終えて、正気と狂気の境界にある、かたい部分にしなやかに手を伸ばす寓話的な緊張感に、多少酔ったようになりながら、ふうと息をついて本を閉じた。この本が書かれたのは64年で、ベトナム戦争はそれから10年続いた、というあとがきに、小さな絶望を感じて、雨脚の弱まったコンクリートの車道を見つめた。コンクリート舗装の下の、50年前のベトナムの土を想像してみるがうまくイメージできない。
私はもう一度本を開いた。扉には「何があっても応援してるから」裏表紙には「おまえには世界が似合う」と書かれている。
この本がよもや、自分が海外に出るときの貰い物だったとは思わなかった。というか、貰い物であるということもすっかり忘れていた。ベトナムで読み始めてしばらくしてこの手書きコメントを見て、この本をもらった東京での飲み会のことを思い出した。その飲み会のぐだぐださと多幸感と、小さな安全の感覚を思い出した。飲み会の一週間後に私はベトナムにいて、麺をすすったり、孵化する直前のアヒルことゲテモノのホビロンを食べたりしたのだ。それらに大げさに感動して、つよく東京からの解放を感じたのだ。もう、6年も前のことだ。
あのときの飲み会にたくさんの勇気をもらっていたのだということを、6年を経た今ももらい続けているのだということを、さっとまるで当然のことのように、ずっと知っていたことであるかのように思う。6年もこの本をほったらかしにしていたくせに、書いてもらったコメントもずっと忘れていたくせに、ついでにもう一冊もらった本もまだ読んでいないくせに、でかい顔してそう思う。

帰り道ぼーっと歩きながら、露店につまみ食いをしようと押し入った。店先、肉まんと同じ場所に、無害な顔をした白い卵がいくつか置かれていた。私は6000ドンを払ってその卵の中からにゅるっと這い出たホビロンを食した。6年前はその内臓や顔や羽の原型にウオッと思ったものだが、今回の感想はちょっと見た目エグイけどコクがある卵だなくらいのものであった。みずみずしい感動が失われた代わりに、今の私の中には平らな器ができたのだと思う。10年の歳月、6年の歳月。おとなになった旅。