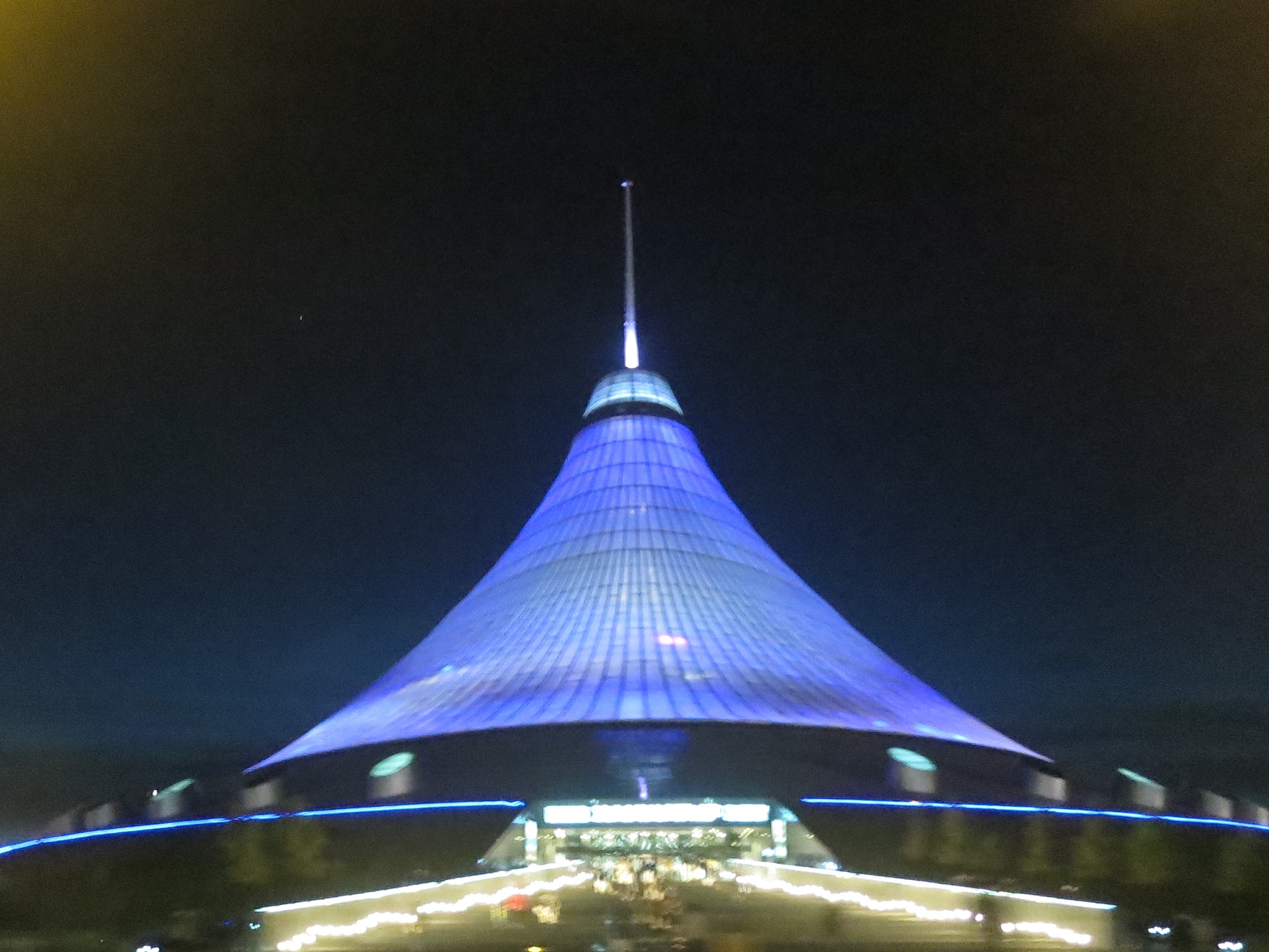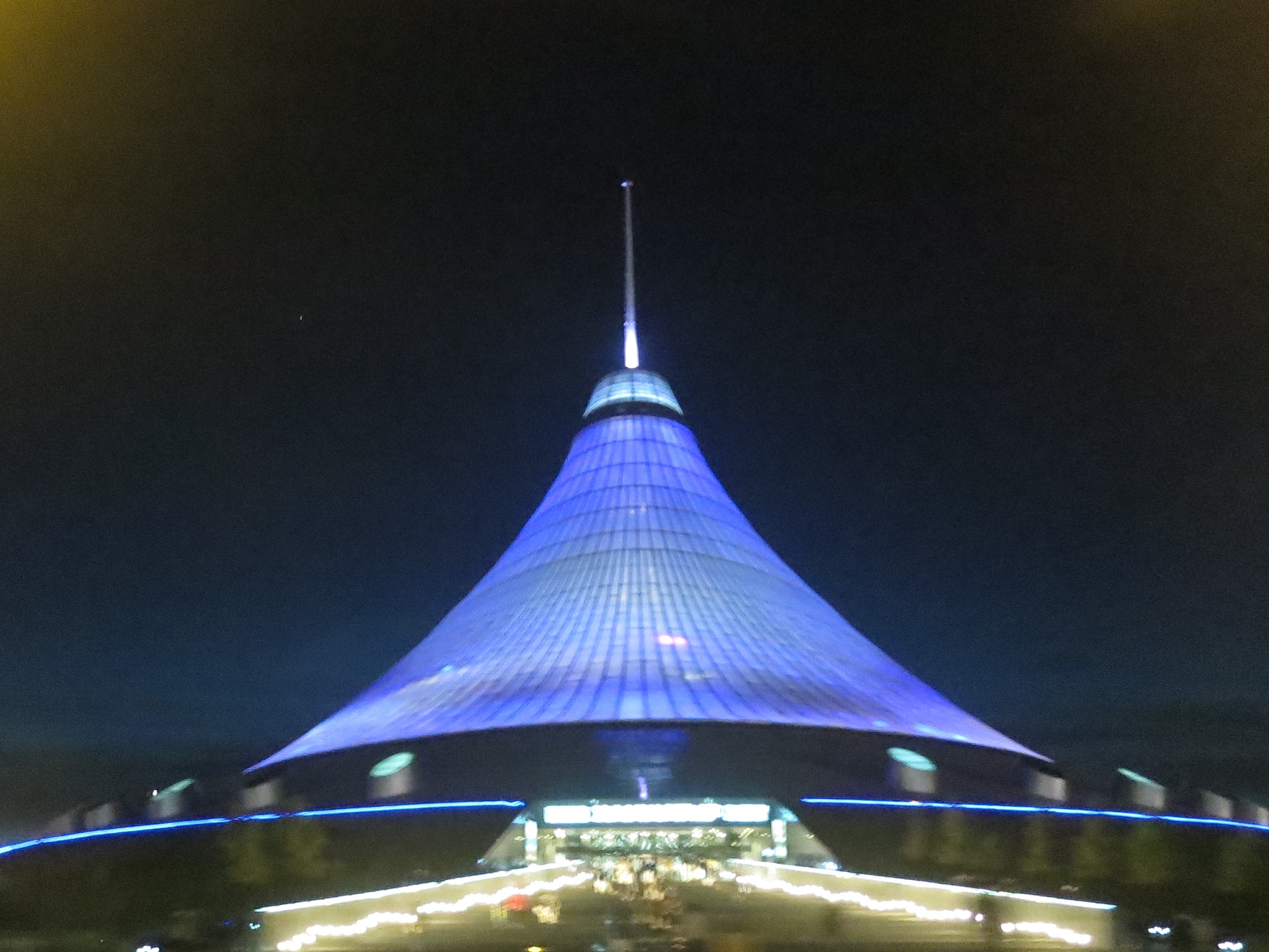カザフスタンに来たところ、アスタナの街があまりに寒く、暖をとるために国立博物館に寄った。
そうすると歴史民俗ゾーンには先史時代の「黄金の間」なんかがあって、大昔のユーラシアの財宝が残っているようなところはロシアの博物館とも似ているのだが、その後、順路をたどって歩き回っているうちに、気づくと19世紀になっている。間にあるはずの、中世だとか近世だとかいう言葉で表現されている(はずの)時代がぽっかりと抜けていて、そのかわりにただ、大きなゲルの展示された部屋があった(カザフではユルトといいます)。
部屋の片隅には中央アジアのシルクロードを横切っていったムスリム商人たちの置き土産的コーランがあるくらいで(いやでもそれをすごいと思った)、他に目を引くものはなく、つまり時を経て残っているであろうものが博物館にしては明らかに不足していた。部屋の真ん中には大きな面積をとって、移動式住居のテントがぴちっと張られていた。大草原の遊牧民の生活を再現するつもりか、あくまでサンプルとして放置される展示用ゲルと展示用の馬を、室内の照明が赤に青に紫にと染めていた。
残るものを歴史というなら、残らないものは歴史ではないのかというとそうでもあるけれどそうでもなく、ポーネグリフは石だけではなく、書かれない時間は書かれないなりに空白を作り出したりもしていて、その空白に、ふっと、自由だと思った。その、創り出されたスペースを、きもちよいなと思った。私は空白が好きだ。

カザフスタン人の多くがダウンロードしているアプリに、ジュズ(部族)の家系図をたどるアプリがあるらしく、土地にではない場所にアイデンティティを持つのは遊牧民だった彼らにとってはたぶん当たり前のことで、それをなんてすてきなんだろうと思っていた。
ところがその後、アフリカに来たところ、空港に降り立ってむんとする熱っぽい空気を吸い込んで、そのときにこれはもうただいまなのだと知って、どこからがただいまになるのかはよく分からないけれども、どこにただいまと言っているかもよく分からないけれども(大陸か?)、そのただいまの感覚に激しい安堵をおぼえ、私の中には土地に紐づいているアイデンティティもたしかにあるのだ。と思った。
だから地球がさかさになって空の中に振り落とされても、その蜘蛛の糸のような紐をたよりに、てきとうな場所を見上げて二日酔いをさますに違いないのだ。私は空白が好きで、でも自分は空白だけからは構成されていないことを、知っていると思っていたけど改めて知ったような気もする。